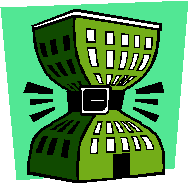 内部統制
内部統制
内部統制とは コーポレートガバナンスとは コンプライアンスとは など、ビジネス基本用語を時系列で解説
■企業経営キャッチフレーズの流れ
その昔、会社とは個人が設立した私的なものだから何をやっても勝手だ、と認識されていました。
しかし現代では、企業も公的な存在であるという認識が高まりました(社会の一員。上場企業とは不特定多数が株主になれるpublicな存在)。
この流れから次々に、コーポレートガバナンス、コンプライアンス、内部統制といったキャッチフレーズが登場しました。現在、もっとも関心が高いのは「内部統制」です。法制化されたため、規制を守らないと経営者は罰せられます。
企業による不正を防ぐことで投資家・社会を守る規制が増えました。企業もこれらの規制を守る立派な会社であることを投資家にアピールしています。
■1970〜 企業の社会的責任(CSR)とは
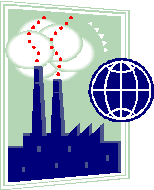 企業が環境問題などで社会に貢献すること。
企業が環境問題などで社会に貢献すること。
フィランソロピー(philanthropy、社会貢献、企業の慈善活動)やメセナ(スポーツ・文化・芸術支援)と昔は呼ばれていました。それが時代とともに、単なる慈善ではなく、「責任」や義務として進化したものです。
CSR
= corporate social responsibility = 企業corporationsは積極的に社会society(顧客・株主を含む)に奉仕する責任responsibilityがある、当たり前のことだ。
企業は利益profitsのことを考えるだけでなく、社会に貢献すべし。そうでなくてはこれからは(企業を見る消費者の目が厳しくなったから)生き残れない。
典型的には、環境問題での社会貢献。
似ている SRIとは
socially responsible investment 社会的責任投資。どの企業に投資しようか選ぶときに、環境問題などに取り組んでいる倫理的な企業を選んで投資すること。
CSRは消費者からみたもの。SRIは投資家から見たもの。
年表
ベトナム戦争 バークレー校 反戦運動 ヒッピー →退職してCalPERS加入、2000年、環境破壊などの企業は投資しないように =
SRIの始まり
ダウ・ケミカルがベトナム戦用にナパーム弾 →反対市民が株主になり中止提案。70/7最高裁で「提案は有効」
= 米でCSR概念が最初に登場
2000 日本のCSR元年 雪印食品の牛肉産地偽装 安全性とは関係ないが、消費者から非難
CSRとは 日本経団連の具体例 Corporate social responsibility
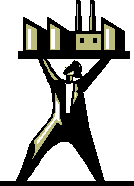 ■コーポレートガバナンスとは
■コーポレートガバナンスとは
=
会社運営のルールを(自治体並みに)きちんと作ること。CEO・取締役会といった会社組織法から、個別の会社のルールまで。よいコーポレートガバナンスを達成する体制が内部統制
corporate governance(企業統治)
govern(統治する)は、もともとは政府・地方自治体に対して使われる言葉です。
地方自治体が法律などのルールをこまかく整備してgovernされている仕組みをまねて、企業においてもきちんと統治governする仕組みcorporate governance mechanisms
を作ろう、というのがコーポレートガバナンスのイメージ。
会社組織法・意思決定・経営チェック・情報開示などを指します。大昔から使われている一般用語なので定義ははっきりせず、広い意味で「会社をきちんと統治すること」として使われています。
米国では各州により会社組織法が違い、コーポレートガバナンスは微妙に異なる。OECDは1999年に OECD Principles of Corporate Governance.を作り、
2004年に改訂。
コーポレートガバナンスで大切なことは、honesty, trust,
openness, accountability, mutual respect,
倫理、株主とほかの利害関係者の尊重、内部統制、外部規制、組織体制(CEOが執行、重要な決定は取締役会の了承)など。
リング: コーポレートガバナンスとは コーポレートガバナンスの例 コーポレートガバナンスとはなんですか ウィキペディア
 ■1990年代〜 コンプライアンスとは
■1990年代〜 コンプライアンスとは
= 談合などの企業犯罪を積極的に防ぐ担当者を置くこと。
compliance(法令順守)
談合・粉飾・隠蔽など、企業による犯罪が続きました。この反省から、企業はコンプライアンス担当者・担当課を置くようになりました。
complianceとは、法にcomply(従う)こと。
1989 リクルート事件(社長逮捕)
2000 三菱自動車工業 リコール隠し発覚
2002 牛肉産地を偽装した雪印食品が廃業に
2005 西武鉄道グループの堤義明氏逮捕
2006/1 ライブドア粉飾決算で堀江社長逮捕
2006/4 公益通報者保護法 (企業内での不正・反倫理的行為を外部へ通報した社員を守る)
2006/6 損害保険ジャパン 保険金不払いなどで業務停止処分
リンク: コンプライアンス コンプライアンスって
■1990年代〜 リエンジニアリングとは
複雑になってしまった会社の組織やルールを抜本的に見直し、再設計(リエンジニアリング)してしまおうとする企業改革。縦割り組織のフラット化が特徴で、いろいろな役職をシンプルに変えた企業が続出した。
1990年のHarvard Business Review誌に発表された論文が原点。1993年に"Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution"がベストセラーとなり有名に。
■ステークホルダーとは
stakeholders 利害関係者。
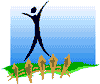 原義: stake =
stickで、木の杭を土地に打ち込んで、「ここは俺の土地(財産)だ」と主張したもの。賭け金もstake
原義: stake =
stickで、木の杭を土地に打ち込んで、「ここは俺の土地(財産)だ」と主張したもの。賭け金もstake
stakeholder
(1)元の意味: 賭け金(stake)をhold(持って)(勝敗が分かるまで)管理する人。
(2)昔の意味: stakeholderは「株主(の1人)」
(3)今の意味: 意味が広くなり、かかわりのある人・団体・国(すべて)を指す。ビジネスの文脈では、株主、従業員、消費者、取引先、地域社会。
stakeholder
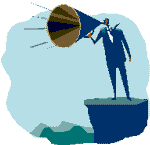 ■ IRとは
■ IRとは
investor relations (企業広報をぐんと増やして)株主との関係(をよくして株価を高めること)
積極的に広く深く企業の経営内容や経営理念を知ってもらうこと。「事業報告書(アニュアルレポート)」「会社案内」などを株主に送付。ウェブサイトへの掲載。株主や投資会社との対話。
昔は、法律で決まっている報告書だけ、株主総会のときに株主に送っていた。あとは株主のことはおかまいなし。
これを積極的なものにすると IR
で、どんどん会社の情報開示・PRを行い、投資家を広く引き寄せて株価を高める。充実した英文ホームページを持つことによって海外からの投資を引き付ける会社が増えました。
■2002- 内部統制とは
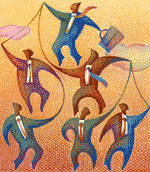 「正しい会社」であることを保障する管理体制を文書化すること。違法行為防止の管理体制、職務分掌、業務マニュアル化、ITセキュリティーなどの義務化。内部統制とは、これまでの言葉で言うと、会社の「管理」のこと。
「正しい会社」であることを保障する管理体制を文書化すること。違法行為防止の管理体制、職務分掌、業務マニュアル化、ITセキュリティーなどの義務化。内部統制とは、これまでの言葉で言うと、会社の「管理」のこと。
目的は粉飾を防止(財務諸表の信頼性の確保)し、投資家や経済を守ること。企業の不祥事が続き、「企業はほうっておけば悪いことをする」ので規制しよう、ということです。
1992-94 内部統制(internal control)を米COSOレポートが強調。
通常のcontrolとは、外から誰かがコントロールするものですが、会社の体制を内部からきちんとすることで統制し(管理し)、問題を未然に防ごう、という考えです。このためinternalという言葉が付いています。強制的にやるのでcontrolという言葉を使っています。
大和銀行株主代表訴訟(ニューヨーク支店のデリバティブ取引を1行員にまかせ巨大損失)で大阪地裁判決00/9/20、取締役11名に対してなんと829億円の賠償を命ず →「リスク管理体制」が問われるように
2001-2 米でエンロンとワールドコムが巨額粉飾で破綻。負債はそれぞれ160億ドル、410億ドルと巨額で、米経済は混乱。両社は内部統制がいいかげんで、法律が守られなかった。
→2002 米でSOX法
提唱議員の名からSarbanes‐Oxley Actと呼ばれる
内部統制の構築義務化 財務内容が正しいことを証明させ、違法行為のチェックをさせる
違反経営者には厳罰 禁固25年
01/12エンロン不正発覚、2ヵ月で破綻。それでもSOX法には産業界から強い反対があったが、上院採決直前にワールドコムのスキャンダルが発覚して成立。1930年代以降でもっとも大きな改革、とブッシュ大統領が02/7/30署名式で。
→日本でも2006/5施行「会社法」と2006/6成立「金融商品取引法」(旧 証券取引法)が内部統制を義務化。
会社法(商法・有限会社法などを一本化) 内部統制の基本方針の決議を要請。罰則規定はない。義務に違反すれば株主訴訟を起こされることはある。
通称「日本版SOX法」 = 金融商品取引法
内部統制報告書の提出・監査
提出しなかったり、虚偽の報告書を提出した場合、経営者は5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または両方
上場企業と子会社を対象 2008年3月期から適用
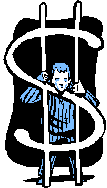 つまり、経営がまずいことは、犯罪になったのです。
つまり、経営がまずいことは、犯罪になったのです。
また、上場企業はこれまでは年1回、政府に有価証券報告書を提出していましたが、今度から内部統制報告書・監査書も提出することになったわけです。
内部統制のガイドライン 企業会計審議会内部統制部会が作成中 「実施基準」(2007年決定へ) 予想事項:
違法行為や不正が起きない職務分掌(仕事の責任・権限を文書化)と管理体制
仕事の手続き・処理規定・マニュアルなど文書化
ITセキュリティの強化・アクセスコントロール
危機管理などの規定の整備
従業員や外部委託先など協力会社の管理、教育
内部統制とは「きちんと会社を管理する合理的なシステムを作りなさい」という抽象的なことです。具体的に各会社でどんな内容の内部統制の制度を作るかは各会社の自由で、千差万別になります。決まったやり方があるわけではありません。
リンク: 金融商品取引法成立 内部統制とは 日本版SOX法
サーベインス・オクスレー法
Wikipedia
■内部統制構築のステップ 構築・評価・監査・開示
(1)全社的な内部統制
行動規範、取締役会・監査役会(が機能しているか)
(2)各部ごとの内部統制
自分の会社のどの部にどんな財務リスクがあるか対象業務をリストアップ。
自分の会社のどの部にどんな法令違反がありえるかをリストアップ。
→業務分掌を決め、対策をマニュアル化 =
内部統制を決定 =
「業務プロセスの文書化」 = 暗黙知を形式知に変換
例:1人だけに取引をまかせチェックがない(大和銀行NY巨大損失事件) →他の人もチェックする
社長が総会屋利益供与を「知らなかった」(神戸製鋼所株主代表訴訟) →不正経理のチェック、報告の義務付け
(3) ITセキュリティの内部統制
システムの管理
(4)会計年度末ごとに内部統制報告書を作る。有効かどうか経営者の自己評価を付ける
(5)外部監査人(公認会計士)が監査 →内部統制監査報告書
中間監査をしてもらい、問題点があれば直す
(6)有価証券報告書とともに内閣総理大臣(窓口は財務局 = 財務省の出先)に提出。開示される
■日本版SOX法の全体
(1)金融商品取引法(の関連部分)
→内部統制報告書 内部統制監査報告書
上場会社と連結会社
(2)「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準案」(金融庁05/12公開) 評価方法・監査方法
(3)実施基準(具体的ガイドライン)
■法律の条文
会社法 第362条
6.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保(注:内部統制を指している)するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
....
5 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第6号に掲げる事項を決定しなければならない。
会社法施行規則
(平成十八年二月七日法務省令第十二号)
第百条 法第三百六十二条第四項第六号 に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
一 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
四 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
五 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
2 監査役設置会社以外の株式会社である場合には、前項に規定する体制には、取締役が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
3 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。
一 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
二 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
三 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
四 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
■参考資料 日経ビジネス増刊06/11/28「会社を強くする 正しい! 内部統制」
■■そのほかのビジネス用語から
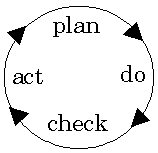 ■PDCAとは
■PDCAとは
plan→do→check→act 計画−実行−評価−改善 のPDCAサイクルで、品質を向上させ続けること
計画を作って実行するまではいいが、そこで止まってしまう例が多い。成果をチェックし、実情にあったさらにいい計画を実行。
戦後日本は、まだ品質が悪かった。そこでデミング博士を通産省が米国から呼んで広めたのがPDCAサイクル。
■SWOT分析とは
商品をStrength, Weakness, Opportunity, Threatの4分野で分析すること。 ACCIA IT情報マネジメント事典
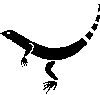
■とかげのしっぽ切りとは
社長の責任の取り方の1つ。現場の担当者を処分して、社長は居座る。とかげは敵にしっぽを捕まえられても、しっぽを切って逃げ、なんともないところから。
■■会計・経理用語
■有価証券報告書とは
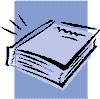 上場企業(4500社ほど)が提出を義務付けられている決算書のこと。株式会社の「株」券は有価証券の一種。
上場企業(4500社ほど)が提出を義務付けられている決算書のこと。株式会社の「株」券は有価証券の一種。
多くの場合、有価証券報告書 = 財務諸表 = 決算書 として言い換えられている。
厳密には、
財務諸表 = 財務三表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書)など に加えて 会社の沿革など詳細に記した書類。
決算の集計は通常1年間(決算年度)。この末日が「決算日」
決算3ヵ月以内に財務局に提出。3月末決算ならば、多くは6月に株主総会で決算承認、政府に提出。決算公告
として日経新聞や官報などへの掲載が義務付けられている。
虚偽の財務報告(粉飾)には、経営者は懲役10年以内または1000万円以下の罰金。法人には7億円以下の罰金。
企業情報概要はヤフーファイナンスで見られます。有価証券報告書等は金融庁のEDINETで閲覧できます。各企業がウェブ上で公開していることも。有価証券報告書とは・調べ方
■SGA
= Selling, General and Administrative expenses 「販売費及び一般管理費」 営業費とも。
Selling: 売るための経費 =
販売・広告員の給与と経費(交通費・広告費を含む)
General: 一般業務にたずさわる社員の給与・経費
Administrative: 管理をする役員などの給与・経費
と考えると分かりやすいのでは。販売と、一般管理にかかる費用ですので、家賃、交際費、福利厚生費、通信費、運搬費、保険料、水道光熱費、保守修繕費、備品費、研修費なども含みます。製造コストは含みません。
売上 − 売上原価 = 売り上げ総利益 = 粗利益
売上総利益 − SGA(販売費及び一般管理費) = 営業利益
■リンク
証券用語解説集(野村證券) 経理初心者おたすけ辞書
■グループウェア等
NextWise ビジネスソフトを無料で提供。スケジュール、社内アンケート、関係者以外立ち入り禁止ブログ、オンライン会議、日報

