防災備蓄・防災用品
■水の備蓄
●1人1日3リットルで3日分 高層住宅は7日分が推奨されている(ライフライン復旧に6日かかると試算されているため)
●水道水も短期備蓄できる
塩素の消毒効果によって、常温で3日間、冷蔵庫で10日間程度保存できる(東京都水道局による)
●氷として備蓄
冷凍庫で水を凍らせておく。災害停電になったときに(1)冷蔵庫へ移すと、傷みやすい食品を延命できる。(2)氷が解けたら、飲料水として使えるので一挙両得
市販の水や麦茶で冷凍可PETボトルのものを入れておけば、かなり長期に備蓄できるはず。冷凍によって膨らんでも破裂しない余裕のある形状のボトルなら大丈夫だろう
●備蓄用には「軟水」を
カルシウム、ミネラルなどの含有量が少ない「軟水」がいい。日本産の水はたいてい軟水だが、海洋深層水には硬水もある。表示の「硬度」が100mg/l
以上ならば軟水。硬水は料理に不向き、粉ミルクが溶けにくい
●防災ゼリー
朝日新聞2018/9/28夕p1 「水の心配不要 防災ゼリー」より以下引用:「水がなくても食べられる。……。「宇宙食」として採用される可能性も……。 「LIFE JELLY」 …。 …ビタミンを摂取できる。乾パンと違って口の中の水分を奪われず…。「ワンテーブル」 … 5年の賞味期限…。」
●断水時に水をもらえる場所
以下は、東京都水道局の場合。これらの場所には「災害時給水ステーション」というマークが設置されている
(1)災害時の給水拠点が都内に206カ所ある
東京都水道局「災害時給水ステーション」ページでわかる 例:お台場に最も近いのは江東区の「有明給水所」(=水の科学館)
事前に指定された消火栓などには仮設の蛇口が設置される
(2)給水車
(3)仮設給水栓 避難所付近のあらかじめ指定した消火栓等に、区市町が仮設の蛇口を設置し、開設
「非常用給水袋 感想」で検索 「日本製袋 給水袋」で検索 「非常用飲料水袋 背負い式」で検索
・断水時に料理するときは
ポリ手袋 手を洗わなくても食中毒を防ぐ
ラップ を食器にかぶせる
キッチンはさみ で食材を切る =まな板を使わずに済む
■防災備蓄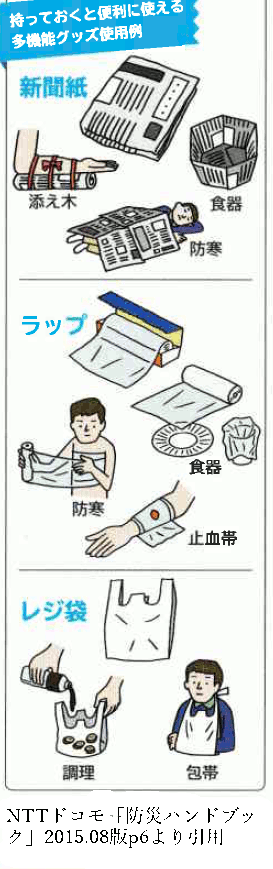

レインウェア
雨だけでなく防寒・風・ホコリにもなる
レインウェアをつなげれば、ママコートになる
防寒 バッグに足を入れて暖める 新聞紙を腹巻・布団代わりに
新聞紙
トイレに。お小水を染み込ませてポリ袋で密閉など
広げて毛布の代わり。腹巻の代わり
丸めて、骨折の添え木に
ティシューを濡らせば、ウェットティッシューになる
ガムテープ
用途が広い。傷の止血、簡易トイレ制作時の固定、連絡先を書いて自宅ドア(の内側)に貼ってから避難
軍手 滑り止め付きがベター
●非常用品備え
重いものは後で取りに帰る
持ち出し袋は、建物が崩れても取り出しやすい場所に置いておく。クルマのトランク、げた箱など
ごみ袋はカッパや防寒着、水をためるタンクに変身
圧力鍋は水不足でも料理ができる省エネ
非常用品
■ローリングストックに適した食品 非常食に適した品 =長期保存
常温で保存できて、そのまま食べられるものがベスト
非常食は循環備蓄しておく =「日常備蓄」とも
食べ慣れないものより、日ごろから食べている缶詰やレトルト食品を多く備蓄して、古いものから食べたら、補充(「ローリングストック」「循環備蓄」)
●災害時に食べる順序 まず冷蔵庫に入っている食品 →次に冷凍庫に入っているもの →最後に常温保存食品
ホイッスル
国の防災基本計画が推奨する家庭の備蓄食料は「3日分」。首都直下の大地震対策では「最低3日、推奨1週間分」
★特に適しているのがレトルト食品
進歩して缶詰のように長持ち。水分を含んである。温めなくてもおいしいものが適する。
「備蓄 レトルト食品」で検索 Izameshiシリーズ
乾パン、レトルト(お粥など)、缶詰
「カンパンクラッカーは水分がないと食べにくいが、ツナ缶などをのせればたべやすく」(朝日新聞2018/9/11より引用:日本災害食学会)
アルファ化米(乾燥米飯、水で戻す) 無洗米が便利
朝日新聞2018/9/11より引用:「日本災害食学会…のお勧めは…アルファ米を野菜ジュースで戻す…。…1時間ほど置けばリゾット風に」
主食(米)の代わりに、シリアル、小麦粉、ホットケーキミックスでも代用できる
せんべい
うるち米で腹持ちがよい。ゴマせんべいなら、ゴマの栄養
塩分の多いものは避ける。喉が渇くため
農水省 家庭用食料品備蓄ガイド コメを中心とする
野菜ジュース
カゴメ、賞味期限5年の「野菜一日これ一本 長期保存用」
マルチビタミン剤 エネルギー補給ゼリー
ロングライフ牛乳
◎カレー
ハウス食品 「温めずにおいしいカレー」 東日本大震災の際に「冷たいままでも食べやすかった」
江崎グリコ 「カレー職人 常備用」 固まりにくい植物性油脂を使っているらしい
*普通のレトルトカレーでも、冷たいままで食べて問題はない。レトルトは完全調理済み、食中毒菌も殺菌済みなので、おなかをこわしたりはしない。
。ただし動物性油脂が固まる・分離するため、おいしくない。あたためたほうがおいしい。→せめて、レトルト袋をよく振ると食感が改善する。あるいはスプーンでかき混ぜる。
なお、ごはんがあたたかければ、カレーを上にかけておくだけで温かくなる。
◎缶詰は3年が標準的 缶詰 マルハニチロ 「アジアン味」シリーズ 若者にも食べやすい
お菓子類 防災森永による:
キャラメル(水分少ないので保存性がいい。高カロリー)
ビスケット(乾パン含む。適度なボリューム感)
チョコレート(高カロリー。気持ちが落ち着く)
ゼリー飲料(食器不要で手軽)
・井村屋 「えいようかん」 糖度を高めてある
「非常食 ライス」(アマゾン
暖めないと、かたい
朝日新聞デジタル 「台風で停電でも温かいごはん パック活用、鍋でも炊ける」によると、「パックご飯はコメのでんぷんがボソボソした状態になっているので、冷たいままではおいしくない。温めることで、軟らかな状態に戻る。」
・出典/リンク
日本災害食学会 日本災害食認証制度
朝日新聞デジタル 「備蓄食、食べて買い足す お弁当に常温カレー、若者へアジア料理」2015年3月11日05時00分で取り上げられた長期保存できる通常食品は上記リンクにあり
■のみ込みにくいときのコツ
・配給のおにぎり・パンが年配者にはのみこみにくいとき
→水分や油分を加えて柔らかくする:
おにぎりは、野菜ジュースにひたす ツナ缶をオイルごとかける
パンは、ちぎって牛乳・コーヒー・果物缶詰・スープにひたす
即席めんは、めんをくだき、長くお湯にひたす
レトルトのハンバーグは、 マヨネーズ・サラダ油を足して、もむ
とろみ調整剤 を加える 食べ物・飲み物が飲み込みやすくなり、誤嚥防止になる
■災害時のトイレ
●仮設トイレは間に合わない
避難所などで仮設トイレを設置し実際に使えるまで数日かかる
●市販品が便利
「簡単トイレ」
単体でもトイレとして利用できるし、通常のトイレにはめても使える「サニタクリーン」便袋 高速吸収凝固シートが便や尿の水分を吸収し、凝固、防臭・防疫
普段使いも優れもの 災害で頼れるアウトドア用品11選(Nikkei
Style)より以下引用: 「携帯トイレ&超防臭チャック袋 ...便や尿を固めて非常時も安心(サニタクリーン)
......携帯トイレは広げるだけで使えるが、洋式便器にセットすることもできる。「これとポンチョを非常持ち出し袋に入れておけば、ひとまず用を足せる」
......密閉できるチャック袋は臭いや水分を漏らさず、丈夫で繰り返し使用できる」
「防災用トイレ JACS」
単なる黒い袋でなく、「強化フィルム袋」なので安心感
●自作もできる
「ビニール袋と新聞紙で作る 簡易トイレ」(NHKサイトなど。動画が分かりやすい)
ストックしておくもの(1)ゴミ用の大ポリ袋、(2)新聞紙(いつも一束は捨てずに置いておく。新聞紙は防寒にも使える)
(A)ポリ袋の内側に新聞紙をセットすると、和式便器のように使える。ポリ袋のふちを外側に折り込む。新聞紙をくしゃくしゃにしてなじみやすく、吸収しやすくしてからサイドを立てる(もれにくくなる)
(B) 洋式便器に45リットルぐらいのポリ袋をガムテープで固定。(便器内にある水は、下水からの匂いを防ぐのに必要。一枚目のポリ袋は、この水で濡らさないためのもの)。その上にもう一枚ポリ袋をかぶせ、底に新聞紙。さらに、吸水しやすく裂いた新聞紙 →トイレ用消臭スプレーをかける
(C)丈夫な段ボール箱があれば、簡易洋式便器(非水洗)を自作できる。内側に大型ポリ袋を敷き詰め、箱上部を丸く切り取る。臭いものには蓋
・野外の場合は、大きいポンチョを着ると、外から見えにくい
・使用済みのポリ袋は、ごみ収集が復旧するまでベランダ等で保管
朝日新聞デジタル 「大地震に備える:4 トイレはどうする? 健康に直結、便袋の準備を」 2016年3月6日05時00分によると:
(1)「備蓄は水、食料、トイレがワンセット」
(2)「市販の便袋を備蓄…。新聞紙などで代用するのは、あくまでも緊急」
(2)手を洗う水の代わりに、アルコール消毒液や除菌シートを備蓄
トイレ凝固剤がないとき →代用は保冷剤(種類による)を少しやわらかい程度に乾燥させる。(塩をかけると早い→コーヒーフィルターでこす)
災害用トイレガイド(日本トイレ研究所) いろいろな製品を紹介
■電池・発電・充電
電池もローリングストックしよう
■防災グッズ ヒット品
●救助笛
★ウィンドストームホイッスル 世界中で最も大きな音
防災アドバイザーが「多くを試した末、…最高だと判断したのは米国沿岸警備隊が使うストームホイッスル。……嵐の中でも聞こえる……を小型化…。……この笛を「命の笛」と呼んで普及を図っているのが「命の笛運動本部」」 朝日新聞デジタル 「防災用品:1 生死にかかわる笛の音」 2015年12月12日03時30分より。
幅6.5cmなので、大きいという感じる人も
★防災用救助笛 ツインウェーブ
人の耳に聞こえやすい二種類の周波数の音を同時に発生 うるさい所でも聞こえる
・ほかにも、小型で大きな音が出せる笛が市販されている
●たためるヘルメット
・タタメット
軽く、普通のヘルメットの1/4の厚みに 普段は本のように会社の引出しにもしまえる。折りたたみは簡単
★タタメットズキン タタメットの後ろに銀色の防災頭巾が伸びている。小学校などで、伝統的な防災ずきんの代わりとして採用されている
タタメットの長所はコンパクト性、気軽に「備えやすい」点。頭巾付きは火事でも安心
弱点もあることに留意。丸型ヘルメットほど保護性が高くない、というか、かなり劣る印象。三角形なので、どうしても斜め上からの衝撃はたちまち頭に伝わる(ヘルメットと頭の側面が近く、頭にぶつかる)。これは実際にかぶって横を叩いてみるとすぐ分かる。このためか、認定は「飛来物・落下物用」であり、「墜落時保護用」としては認定されていない。自転車運転にはまったく適さず、自転車は横に転倒するのでケガをする
また、三角形なので頭が奥まで入らないため安定が悪く、紐もゆるい印象。三角形なので頭には浅く、江戸時代の笠みたい。それでも、頭に何もかぶっていないよりは、はるかにましだろう
・たためるヘルメット各種
●進化した消火器
消火器 キッチンアイ 一般的な消火器からは、粉が噴出するが、キッチンアイからは液体(酢のようなもの) 粉と違い、再着火しにくく、清掃しやすい
●パック食品を温める 水をそそぐだけで
モーリアンヒートパック 加熱セット
●キングジムの「着る布団&エアーマット」
帰宅困難社員がオフィスに泊まり込むために開発された実用品。靴を履いたまま歩ける寝袋とエアーマットのセット。普段はA4サイズで、棚や机の引出しに入れておける。
■噴火対策 (火山灰)
日本では噴火は繰り返し起きているが、富士山噴火は300年以上ないため危機意識が薄く、災害対策としては「想定外」となっている
火山灰(=溶岩の破片)で道路はスリップ、鉄道は走れず、飛行機は飛べなくなる。眼球を傷める。濡れた火山灰で停電、電子機器は腐食、浄化しきれず断水 除去した灰は水に流してはいけない(下水管が詰まる)
家庭では、ゴーグル、防塵マスク、除灰用のスコップを備える
「朝日新聞 富士山噴火 火山灰」で検索
■エレベーターの閉じ込められ対策
普段はエレベーター内のイス。閉じ込められたら、トイレ(目隠しシート・トイレットペーパーなど)、水備蓄
そのほかのエレベーター防災用品
防災用品総合ストア(アマゾン)
■参考リンク
普段使いも優れもの 災害で頼れるアウトドア用品11選 Nikkei
Style
■防災ページ目次

